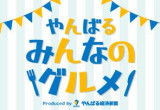大宜味村役場旧庁舎で見学イベント「内部公開デー」 100周年の記念日に

大宜味村役場旧庁舎(大宜味村大兼久)で5月23日、見学イベント「内部公開Day!」が行われた。
沖縄で初めてとなる鉄筋コンクリート造建築として1925(大正14)年5月23日に落成した同庁舎は、同日で100周年を迎えた。これを記念し、普段は非公開の建物内部を一日限定で公開するイベントを開いた。主催は大宜味村教育委員会。
同庁舎は沖縄県内で現存する最古の鉄筋コンクリート造建物で、1997(平成9)年に沖縄県指定有形文化財に、2017(平成29)年には国の重要文化財にも指定されている。建築面積は169.98平方メートルで、海岸から約100メートルの場所に位置し、大宜味村のシンボルとして長年親しまれてきた。
設計は熊本県出身で当時の国頭郡技手だった故・清村勉さんが手がけ、台風やシロアリ被害への対策として、当時は県内で珍しかった鉄筋コンクリート造を採用したという。建物は十字形と八角形を組み合わせた独自の構造で、中央のホールを囲むように部屋を配置。2階には村長室が設けられている。
当日は、同庁舎の歴史を伝えるパネル展のほか、名護市文化財保存調査員で国頭村文化財保存調査委員も務める木下義宣さんによるガイドが行われ、建築様式や建設背景などについて解説した。村民や名護商工高校建築科の生徒、関係者ら約40人が参加した。
ガイドで木下さんは「設計段階では2階の村長室はなかったが、建設中に急きょ追加された」「鉄筋コンクリートの建物は当初は墓を連想するからと受け入れられず、まずは名護市内で公衆トイレを建設し、強度を示した」「海岸の砂や村内の畑の土を材料に使った」などと説明した。
木下さんは「完成から100年のこの日に多くの参加者とこの会を開けたことに感激。清村さんとも生前に交流があったが、今もなお、しっかりと立つこの建物に清村さんの思いを感じる」と話した。
大宜味村教育委員会教育課の寄合龍己さんは「この建物は村の象徴であり、村民に守られ愛されてきたことを改めて実感した。大きな節目となるこの日にイベントを開くことを決めた。来年2月23日には、国の重要文化財指定の日と100周年を記念して、セレモニーを開く予定」と話す。