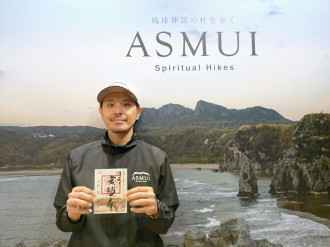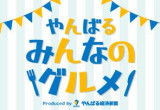シークワーサーの旬に合わせて「青切りシークワーサー初出荷式」が8月5日、本部町伊豆味のシークワーサー畑で行われた。
青切りシークワーサーの収穫シーズン開始に合わせて、消費拡大に向けたPRを図ろうと毎年行うもので、今年で22回目を迎える。主催は、沖縄県や北部地域の自治体などで構成する「北部地区シークヮーサー生産・出荷・販売促進協議会」。開催地は主要生産地域の大宜味村、本部町、名護市から毎年持ち回りで選ばれる。
同協議会によると、今年の北部地域のシークワーサー生産面積は昨年より476ヘクタール少ないが、生産量は昨年よりも245トン多い3055トンを見込む。過去5年間の平均生産量3551トンに比べると、496トン少ない。空梅雨の影響で出荷時期が遅れることを懸念していたが、7月に入り降雨に恵まれたことで例年通りの出荷になった。
当日は、平良武康本部町長ら3市町村長やJAおきなわ担当者、加工業者や生産農家ら約40人が参加。出荷式では、シークワーサーの木から実をもぎ取り、「伊豆味みかんの里総合案内所」での試飲会、シークワーサーを使った加工品の展示紹介も行った。
あいさつで、平良武康本部町長は「今年も大勢の皆さんと共に初出荷式を行うことができた。しっかり実ったシークワーサーの木に感謝する日でもある。県内北部地域で生産量が約3000トンあるシークワーサーに付加価値を与えて、日本全国・世界に売り込んでいきたい」と話した。
生産者の高良久さんは「今年は昨年よりも出来栄えが良い。雨が結構降ったことで一つの実が大きくなり、順調な生育だった。1キロ単価が昨年度の180円から今年は200円へと上がった。農家としてもありがたい」と話す。北部農林水産振興センターの上原弘樹班長は「昨年はカメムシ被害や北部豪雨災害で栽培に苦労したが、今年は十分な降雨に恵まれた」と話す。
青切りシークワーサーの収穫と出荷は9月中旬まで行われ、県内外へ出荷する。